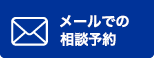1.後遺障害等級の認定方法
交通事故による後遺障害等級の認定方法としては,以下の3つの方法が考えられます。ただし,④の方法については,理屈として考えられるというものに過ぎず,一般的には①から③の方法で認定されることになります。
① 損害保険料率算出機構による認定
② 労災保険手続上の認定
③ 裁判手続における裁判所の認定
④ 事故当事者の合意による認定
⑴①損害保険料率算出機構による認定
ア 事前認定
交通事故加害者(一般的に過失割合の大きい事故当事者)加入の任意保険会社(以下「保険会社」といいます。)が,治療費などの支払いを行なってくれている場合(一括払い。「保険会社の対応に不信感がある」参照。),被害者に対して支払う(支払った)賠償金について,保険会社は加害者加入の自賠責保険会社からの回収の見通しを得る必要があります(保険会社が被害者へ支払った賠償金について,保険会社は自賠責保険会社から自賠責保険が規定する基準の範囲内で回収を行うことができます(自賠法15条))。その場合に,保険会社は,損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)に対して,後遺障害等級の認定に関する事前認定の申請を行うことができます。
この場合,保険会社主導の手続きとなるため,保険会社は医師の意見書(「後遺障害に該当しない」など)を付けて申請することが可能となります。
イ 被害者請求
一方で,交通事故被害者(一般的に過失割合の小さい事故当事者)も,自ら損保料率機構に対して後遺障害等級の認定を申請することができます。この場合,自ら毎月の診断書やレセプトを病院から収集して申請することになるため,それなりの手間と費用がかかります。手続の負担からいうと,上述した事前認定手続の方が負担は小さいと言えます。
しかし,保険会社による意見書の添付などを阻止することができ,場合によっては主治医の意見書などを添付することができるなど,申請手続を主導することができるため,一般的に被害者請求手続の方が被害者にとって有利であると言われています。
⑵②労災保険手続上の認定
交通事故が通勤中や勤務中に発生した場合,労災保険給付申請手続において後遺障害等級が認定されることもあります。交通事故の後遺障害等級の認定基準が労災保険の認定基準を準用しているため,理屈から言うといずれの手続で認定しても同じ結果になるはずです。
しかし,一般的に,労災手続における認定の方が,損保料率機構による認定よりも後遺障害等級が認定されやすい(より高い等級が認定される)と言われています。
⑶③裁判手続における裁判所の認定
上述した2つの手続での認定を受けていない場合でも,認定を受けたもののその内容に不満がある場合でも,裁判手続の中で実質的に裁判所に後遺障害等級を認定してもらうことも考えられます。
ただし,一般的に裁判所は,損保料率機構や労災保険手続における労働基準監督署長の判断を尊重し,それらの機関の判断と同じ内容の判断を行うことがほとんどです。この点,裁判所が損保料率機構の判断や労災保険手続における労働基準監督署長の判断とは異なる判断を行うこともありますが,損保料率機構の判断よりも,労災保険手続における労働基準監督署長の判断の方が裁判所にひっくり返される確率が高いように感じます(前述したとおり,労災手続における認定の方が,損保料率機構による認定よりも後遺障害等級が認定されやすい(より高い等級が認定される)こととも関連しているように思います)。
⑷④事故当事者の合意による認定
本来,交通事故の損害賠償とは,被害者の「後遺症」(回復しない身体・精神機能の不調)によって発生する不利益状態を金銭賠償で処理するものであるため,事故当事者の合意が成立しさえすれば,上述した後遺障害等級の認定手続を踏む必要はなくなります。
ただし,保険会社が上述した手続を踏まずに,後遺障害の存在を前提とし賠償を行うことはほとんどないといえます。そのため,理屈の上で考えられる方法に過ぎません。
2.後遺障害等級の認定に対する評価
上述した方法,特に①の事前認定や②の方法で後遺障害等級に関する認定を受けた場合,その内容が適切なものであるのか非常に気になるところですし,賠償金額を大きく作用する重要な問題となります(①の被害者請求の方法で認定を受けている場合,一般的に,既に弁護士に依頼していることが多いと思われます)。
治療終了後,保険会社から突然「あなたに後遺障害は認められません」,「あなたの後遺障害等級は◯級です。」と言われても,一般の被害者がその内容が適切なものであるのかを判断することは非常に困難であると思います。同様に,交通事故事件,特に後遺障害等級の認定手続に精通していない弁護士にとってもその判断は困難であると思います。
そこで,後遺障害等級の認定内容に疑問を感じた場合,交通事故事件(特に,後遺障害等級の認定手続)に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。